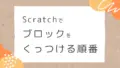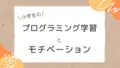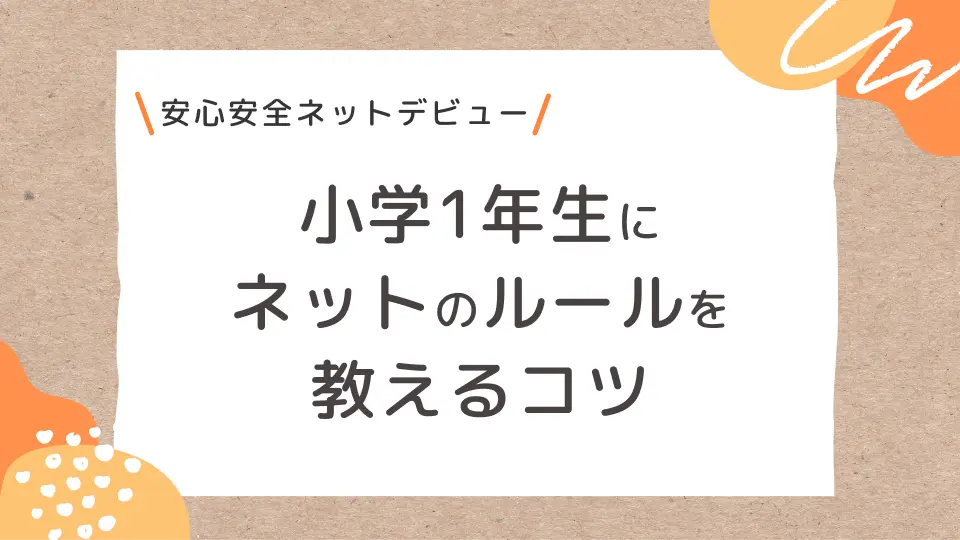
子どもたちのプログラミング教室では、ネット1年生のお友だちに、まず最初にアカウントのルールを教えています。
目の前のアカウントで説明すると、ネットにはネットのルールがあるというのをイメージしやすく、印象に残るようです。
お教室では、以下のように伝えています。

お友だちのアカウントのパスワードを知っていても、勝手に入るのはダメだよ
まずは、自分がしてはいけないことを教えています。
その感覚が身につけば、自分がされたときに「これはダメなことなんだ」と気づくことができます。

車のルールと同じで、まずは自分が人を守ることを習う形です。
ただ、大事なお話でも初めてインターネットを知る子どもたちには、ちんぷんかんぷん。
そこで、この記事では、ちょっとしたコツで子どもたちに理解してもらえる伝え方をご紹介します。
アカウントのルールを伝えるコツは、アカウントを家に例えて、子どもたちに自分事として想像してもらうこと!
アカウントを家に例えよう!
子どもたちに新しい概念を教えるときは、日ごろの生活で子どもたちが目にしているものに例えるようにしています。
アカウント ⇒ 家
パスワード ⇒ 鍵
家や鍵は日ごろから目にしているものなので、アカウントがプライベートな空間であると認識してくれるようになります。

自分のアカウントが自分の家と考えると、勝手に鍵を開けて入ってくるのは抵抗がありますよね。
子どもたちは、自分のアカウントに無許可で入ってこられる抵抗感を感じると、自分以外の人のアカウントに無許可で入ってはいけない理由を少しずつ理解してくれるようになります。
伝えるタイミング
伝えるタイミングは、スクラッチのアカウントにサインインするときにしています(スクラッチについての記事はこちら)。
子どもは、目の前で起きていることに関心を抱きやすい様子があるためです。

経験のなかで学ぶと、実感をもって理解できたりしますよね
伝えるときの注意点!
子どもたちに伝えるときに心がけていることがあります。それは、さりげなく伝えることを数回にかけて行うことです。
薄い水彩絵の具を複数回塗ることで色を出していくプロセスのイメージです。
子どもは、記憶力がとても良く、覚えたことを再現することもすぐにできるようになります。ただ、理解に関しては、大人と同じで一回で理解するのは難しいことも。
さらに、子どもにとって、新しいことを理解するのは負荷が高く、長い説明は拒否や飽きがでてきます。
拒否や飽きがでてしまうと、プログラミング学習自体に拒否感がでてしまいます。
そこで、お教室では、同じことについて軽い説明を少しずつ複数回行うようにしています。

最初は、「アカウントは家みたいなんだよ」とだけ伝えています。
もし子どもたちが興味を持ったら、そのときは興味に合わせて伝えています。
ひとりひとり子どもたちの個性は異なりますので、基本は「観察」を第一に、無理なく子どもの個性に合わせる姿勢が大事です。
安全に楽しくネットの世界で遊べるよう、少しでもこの記事がご参考になれば幸いです。

記事はここまで
お疲れさまでした☆
この記事のまとめ
・ インターネットのルールを教えるのはとても重要
・ 子どもに教えるときはアカウントを家に例えて説明
・ 伝えるのは子どもの関心が向くタイミング
・ 子どもに伝えるときは子どもに負荷がかからない量と回数で