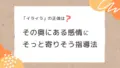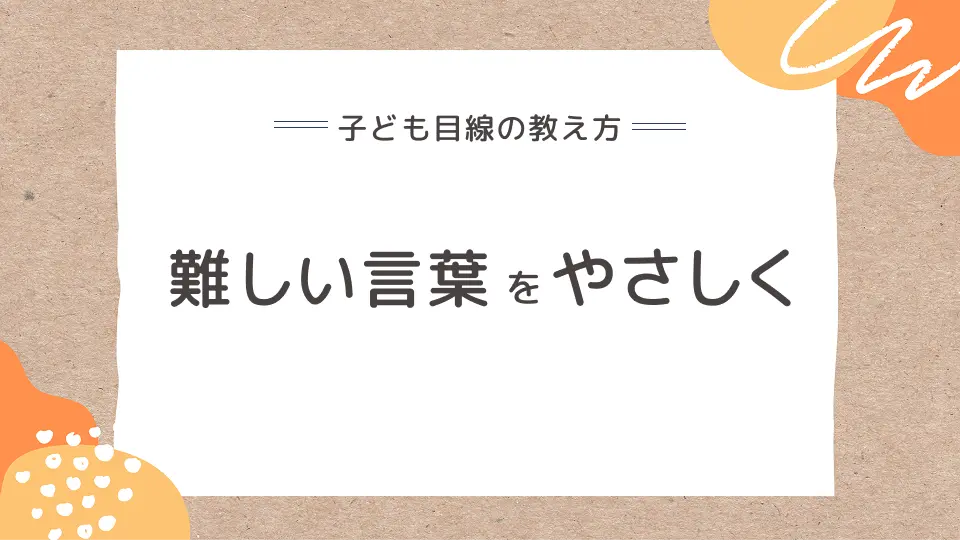
プログラミングを子どもに教えるとき、最初にぶつかる壁は「言葉のむずかしさ」です。
「変数」「座標」「ループ」──
大人にとってはよく使う言葉でも、子どもたちには「まるで異世界の言葉」のように感じられることがあります。
では、どうすれば子どもたちにプログラミングの用語を理解してもらえるのでしょうか?
その答えのひとつが、大人の知っている言葉を子どもが知っている言葉に翻訳してあげることです。

子どもが「わかる!」と思える言葉を選ぶだけで、表情がパッと明るく変わるんです♪
この記事では、言葉の翻訳がなぜ大切なのか、どう工夫すればよいかを、心理学や言語学の視点も交えながら、具体的な例とともに解説していきます!
子どもの理解は言葉を通して育つ
人の思考は、言葉によって形づくられる——この考えは、多くの教育・発達心理学の基盤となっています。
ヴィゴツキー理論:言葉が学びを支える「道具」になる
中でも有名なのが、心理学者レフ・ヴィゴツキーの理論です。彼は、子どもの発達を支えるカギとして、「社会的なやりとりと言葉の役割」を重視しました。
ヴィゴツキーによれば、子どもは、他者とのやりとりの中で言葉を学び、その言葉を“思考の道具”として使うことで、より高度な認知能力を育てていきます。
つまり、難しい言葉を自分なりに説明できるようになったとき、子どもはその概念を本当に理解したと言えるのです。
たとえば、「変数」というプログラミング用語も、ただ定義を暗記させるのではなく、子ども自身がそれを自分の言葉で言い換えたり、例を使って説明したりできるようになって初めて、真の理解に近づいていくといえます。

「わかったつもり」じゃなくて、自分の言葉で話せることが大切なんですね!
言語学の視点:スキーマに結びつけて伝える
言語学的には、「スキーマ理論(schema theory)」という考え方がこれを補完します。スキーマとは、人が持っている知識や経験の枠組みのこと。
「スキーマ理論」では、人は、新しい情報をすでに持っている知識(スキーマ)に関連づけることで、理解しやすくなるとされています。
新しい概念を学ぶとき、その子どもがすでに持っている“意味のネットワーク”にひもづけて説明してあげると、理解はずっと深まりやすくなります。
たとえば、「座標」をいきなり数式で教えるよりも、「地図の上で自分のいる場所を探すときみたいだね」と声をかけることで、子どもの持っているスキーマ(=地図の経験)に新しい知識が自然とつながっていきます。
このように、子どもの知っていること、やったことのあること、見たことのあるものに結びつけながら説明をすると、子どもは「わかる!」「聞いたことある!」と安心しながら学んでいけるのです。

「初めて聞く言葉」を、「知ってる世界」に置きかえることで、子どもの目が輝きます!
自己効力感を守るための「翻訳」
わからない=向いていない、にならないためにも、難しい言葉を簡単な言葉に翻訳することは大事です。
難しい言葉が多すぎると、子どもは「わからない → できない → 自分には向いてない」と感じてしまいます。
これは、心理学でいう自己効力感の低下につながります。
自己効力感とは、「自分にはできる!」という前向きな気持ち。これが失われると、挑戦する意欲そのものがなくなってしまいます。

わかった!の積み重ねが、子どもにはとても大事です♪
実践!プログラミング用語を“子どものことば”に翻訳してみよう
ここからは、よく使われるプログラミング用語を、子どもに伝えるための言い換え例と説明の工夫をご紹介します!
座標(ざひょう)
子どもへの翻訳:「画面の中で“どこにいるか”を数字で表す方法」
説明例:「マス目のあるノートで、“右から5こ、上から3こ”と場所を決めていくイメージだよ。それと同じで、コンピューターの中でも、場所を数字で伝えてあげるんだよ。」
変数(へんすう)
子どもへの翻訳:「中身をあとから変えられる“名前のついた箱”」
説明例:「“おこづかい”って書いた箱があって、今日は500円、明日は800円になるかもしれないよね? 変数は、その“おこづかい箱”みたいなものだよ。」
ループ(繰り返し)
子どもへの翻訳:「同じことを何回もやる命令」
説明例:「ラジオ体操のジャンプって、“1・2・3・4…”って何回もやるでしょ? “10回ジャンプしてね”って、コンピューターに伝えるのがループだよ。」
条件分岐(if文)
子どもへの翻訳:「“もし〜だったら…”っていう決まり」
説明例:「“もし雨がふったら、カサをもっていく”って決まりがあるよね? コンピューターにも“もし〇〇なら□□してね”って伝えるんだよ。」
プログラム
子どもへの翻訳:「コンピューターに“やってほしいこと”を順番に書いたリスト」
説明例:「朝の用意みたいに、『顔をあらう→ごはんを食べる→出かける』っていう順番のメモがあるでしょ?そうやって、やることを順に決めていくことだよ。」
デバッグ
子どもへの翻訳:「まちがいを見つけてなおす作業」
説明例:「お料理で“砂糖と塩をまちがえた!”ってときに、『あっ、なおさなきゃ!』って気づくよね? プログラムでも、うまく動かないところをなおすことを“デバッグ”って言うんだよ。」
指導者や保護者は「翻訳者」
私たち大人は、プログラミングを子どもに届ける翻訳者の役割を担っています。
ただ正しい情報を伝えるだけでなく、子どもがわかる言葉で、伝わるように届けること。
それが、子どもたちが自分の言葉で考え、楽しみながら学ぶ第一歩になります。

子どもたちの様子をみながら、焦らずに伝えていくのがコツです
まとめ:子どもが「できた!」と思える“ことばの橋”をかけよう
専門用語の意味を子どもが理解するには、「ことばの翻訳」が欠かせません。
・ むずかしい用語を、子どもが知っている世界に結びつける
・ たとえ話や比喩を使って、感覚的に理解できるようにする
・ 子どもが自分の言葉で説明できるようサポートする
こうした一歩一歩の工夫が、「やってみたい」「もっと知りたい」気持ちを引き出す力になります!

子どもたちがのびのびとプログラミングを学ぶために、“ことばの橋”をかけてあげてください♪