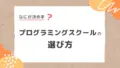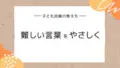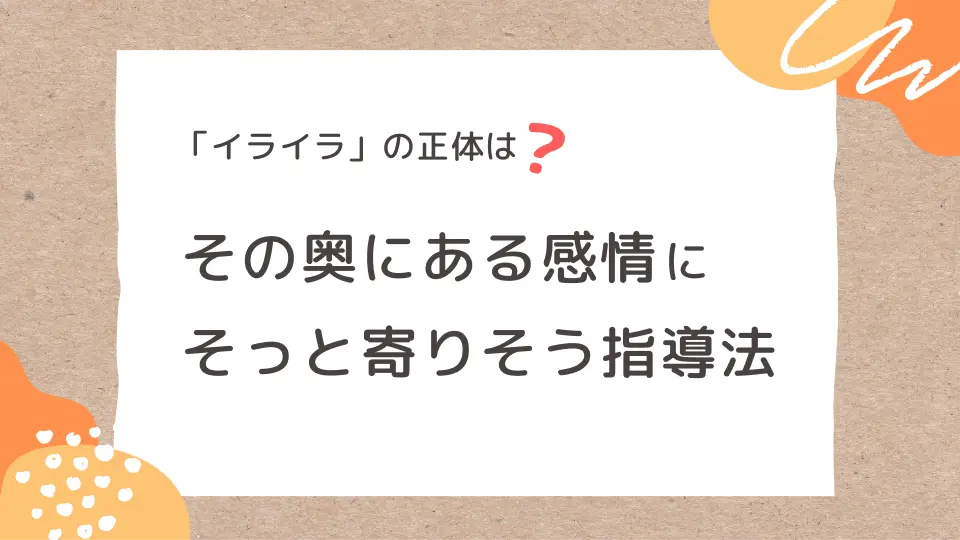
プログラミング教師の私が、日々たくさんの子どもたちと接している中で、「ちょっとしたことでイライラしてしまう子」や「うまくいかないと、つい怒ったような反応を見せる子」に出会うことがあります。
今回は、そういった反応がなぜ起きるのか、そして大人はどのように寄り添えばいいのかを、心理学の視点も交えて考えていきたいと思います。

前提として、イライラや怒ることは自然な反応なので、それ自体が悪いことではありません。
表に出る感情と、本当の気持ちは違うことがある
「キーボードを叩いたり」「プリントをくしゃっと丸めたり」「もうやらない!」と声を上げたり。
教室ではときどき、そんな姿が見られます。
こうした反応を見ると、「怒っている」と感じるかもしれません。でも実は、それがその子の本当に感じていることのすべてではないことが多いのです。
心理学では、怒りは二次感情と言われています。
その奥には、「不安」「混乱」「悔しさ」「恥ずかしさ」「孤独感」など、より繊細でデリケートな感情(一次感情)が潜んでいることが多いのです。
たとえば、こんなシーンを想像してみてください。
初めてのエラーで、どうしたらいいか分からない。
隣の子はどんどん進んでいて、自分だけ取り残されているような気がする。
先生が手伝ってくれたけど、何が起きていたのか理解できなかった。
こうした場面では、「分からない」こと自体がストレスとなり、それをどう表現していいか分からず、結果として「怒ったように見える反応」になってしまうのです。
「大丈夫だよ」と伝えることの力
感情的な反応が見られたとき、大人がまずできることは、「この子、怒っている」と決めつけることではなく、その背景にある気持ちを想像することです。
「わからないことに戸惑っているのかもしれない」
「緊張していて、余裕がないのかもしれない」
そんなふうに考えながら、子どもが安心できるような声かけをしてあげると、ふっと力が抜けたように落ち着くことがあります。
たとえば、こんな声かけが有効です
「難しいところに来たね。いっしょに見てみようか」
「ここは迷う人が多いから、気にしなくて大丈夫だよ」
「よくここまでやってきたね。次はちょっと手伝うね」
こうした言葉には、安心感と共感が含まれています。
子どもの脳は、不安やストレスを感じているときは論理的な思考がうまく働きません。でも、安心できる関わりがあると、脳の「安全スイッチ」が入り、次第に冷静な判断が戻ってきます。
これは、脳の自然なしくみです。
教室は「感情を学ぶ場所」でもある
私たちのプログラミング教室では、プログラミングだけでなく、子どもたちがうまくいかないときの気持ちの整理のしかたや、助けを求める勇気も学んでいけるような環境づくりを目指しています。
子どもたちはまだ、自分の感情をうまく言葉にする力を育てている途中です。ときには不器用な表現になることもあります。でも、そうした場面も含めて、成長のチャンスと捉えています。
「怒ってしまった」という経験も、「うまく気持ちを切り替えられた」という経験も、どちらも大切な学びです。
おわりに
子どもがプログラミング中に思うように進まなかったり、感情的になってしまったとき、大人ができるのは、安心して「わからない」と言える空気をつくることです。
そしてその空気の中で、少しずつ「わかること」が増えていくと、子どもは自然に前向きになっていきます。
わたしたち指導者も、感情の奥にある気持ちに気づき、子どもたちの心にそっと寄り添える存在でありたいと、日々思っています。
この記事のまとめ
・ 「イライラ」は不安や悔しさの裏返し。
・ 感情的な反応は脳の自然なしくみ。
・ 安心と共感の言葉で子どもに寄り添う。
・ 教室は感情も学ぶ大切な場。